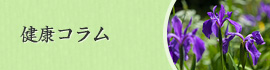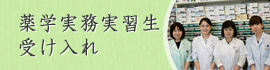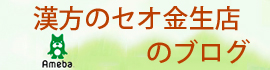“ニンジン ”と聞くと、まず、オレンジ色で馬が好物の野菜、セリ科のニンジンを思い浮かべる方が多いかもしれません。一方、ウコギ科の「朝鮮人参」を思い浮かべた方は健康への知識が深い方かもしれません。今回は後者の「人参」の話です。名称がまぎらわしいのですが、朝鮮人参の他に「高麗人参」、「薬用人参」、「オタネニンジンン」など、使用の歴史に沿って色々の名前がついています。国内では初代徳川家康、八代将軍吉宗などが人参の普及に関係しています。人参は栽培年数により一年根から六年根を目安としますが、五~六年根以上が高級品質とされています。一~三年根は中枢の働きを抑えるディオール系成分が多く、五~六年根ではトリオール系という元気をつけたり長生きに役立つ成分が多くなっています。一~三年が子供の人参、五~六年が大人の人参というイメージでしょうか。生薬の種類として、とれたての生の人参を「水参(すいじん)」、水参をそのまま乾燥したものを「白参(はくじん)」、水参を蒸して飴色状になったものを「紅参(こうじん)」と呼んでいます。紅参は白参に含まれる「マロン酸ギンセノサイド」という血圧を上げやすい成分が蒸して除かれており、血圧を気にされる方は紅参をオススメします。「偽人参(ぎにんじん)」もたまに見かけます。キキョウ、トウキ、ヒュウガトウキなどは根がかなり似た形態をしています。それぞれは目的の薬効がありますが、違う植物ですので鑑別が必要です。ここで「人参の七つの効きめ」をご紹介します。補気救(ほききゅう)脱(だつ)、益(えっ)血(けつ)復脈(ふくみゃく)、養(よう)心(じん)安神(あんしん)、生津止渇(せいしんしかつ)、補肺定喘(ほはいていぜん)、健脾止瀉(けんぴししゃ)、托毒合(たくどくがっ)瘡(そう)、以上。何となく意味が解ると思います。漢方では人参単品を用いた「独参(どくじん)湯(とう)」という処方もありますが、通常は数種を混合した処方で使用されています。代表的な漢方薬としては人参(にんじん)湯(とう)、小柴(しょうさい)胡(こ)湯(とう)、補中(ほちゅう)益(えっ)気(き)湯(とう)など、血行を良くしながら滋養強壮、体力強化を目的に使用されています。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎