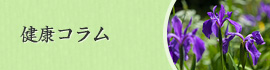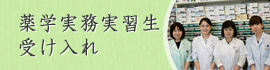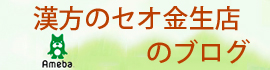ストレス
2021年9月「青い目の姉妹」
若いお母さまから子供の事でお電話がありました。「小学生1年生の長女が風邪をひきやすく、プールの授業を受けさせて良いか?」という問い合わせでした。「直接は本人を見ている担任や養護の先生に相談されたら」とお答えしましたが、「先生(私)が診て下さい」と、午後の帰宅を待ちご来店となりました。年少の妹さんも見え、賑やかになりました。本人ですが、やせ型で日焼けをした普通の小学生でした。風邪をなぜ引くのかわかりませんでしたが、「目が青い」事に気がつきました。白眼が白を通り越して青く見えたのです。「冷え」が入り込んだ結果だと直感しました。また、目が青いのは、肝(疳)の緊張を意味し、落ち着きがなくなります。漢方では肝臓と目は「臓と腑」の関係で影響を受け合っていると見ます。ふと妹さんに目をやると、この子も目がうっすら青く見えました。「子は親の鏡」と言います。お母様のふだんの子育てがちょっと見えた気がしました。子供同士のキンキンした様子はありませんでしたが、まだよくわかりません。さて、プールですが、風邪は天気や気温により、冷えてこじらせることが予想されるので、その日の判断が必要とお伝えしました。特に、あがった後濡れたままの状態では冷えてこじらすため要注意、とアドバイスしました。しばらくお付き合いする事になるのですが、“青い目”の漢方薬と天然アミノ酸の栄養剤で様子を見ることにしました。
肝は目を破る 冷えで目が白青く見える
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師
瀬尾昭一郎
2022年10月「シェーグレン症候群」
「瀬尾先生、何かいい漢方薬がないだろうか?」知り合いの先生から知人の事で相談がありました。漢方薬も症状で三通りほどに分けられます。皮膚や口が乾燥して、煩躁するタイプ、消耗して身体がきつく動けないタイプ、精神的に落ち込み体がきつく乾燥しやすいタイプ。それぞれその方の症状に合わせて使い分けています。それから、補助として天然アミノ酸製剤、天然クマザサ製剤、天然薬用人参製剤をお話しました。その方は、最初のほてりや乾燥がひどいようでしたので、「B」という漢方薬と天然クマザサ製剤をオススメしておきました。「自己免疫疾患」のため、治療には根気が必要です。まずは漢方薬できつい所をコントロールする事。“交感神経が常に興奮(戦闘態勢)”しており、“頑張り屋さん”が裏目に出た状態なので、どこかで休養を組み入れる事(うまくさぼる!頑張っても誰も褒めてくれません・・・)、同じことですが、“短距離走”を“長距離走”に組み込んでおり、一方では体力が消耗、体力を維持する補助剤が必要な事、もし内臓を冷やしている行為があれば免疫には逆らっているので、即刻止める事、等の説明をし、半年から一年様子を見ましょうとお伝えしました。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2023年7月「舌痛症」
女性がほとんどですが、舌の“痛み”や“ピリピリ感”、“味がわからない”等の相談をお受けします。「舌」は、食べたり飲んだりする時、声を出したりしゃべる時無意識に自在に動いています。日頃も、体熱を見る時、胃の具合を見る時、体液を見る時、などに観ています。漢方でも「視診」として観ることにより東洋医学的な診断をします。舌先は「心」、中央部分は「胃」、その奥の部分は「肺」、その両脇部を「肝・胆」、舌全体の最も奥の付根部分を「腎」という配置で色、燥湿、大小など観察します。舌が厚く大きい人は胃も強く食欲旺盛、逆に薄く小さい方は胃も小さく消化の力が弱い。舌全体がボーっと白っぽい人は胃腸や肺の冷え、赤い人は内臓に熱がある、舌の横に歯型がついているのは「気虚」と言って、精神的に疲れている方。舌が震える人、あまりしっかり「ベー」と出来ない人は神経を病んでいる人、貧血の人はオレンジ色が強く、健康なピンク色との比較によりレベルを推測します。舌を上にめくり裏側にある静脈の腫れや色を見ることで、血液のドロドロ具合を見ます。さて、舌の痛みがある方は、精神的なストレスが原因と言われています。味がわからない方は亜鉛不足と言われています。それぞれ何らかの生活習慣から発生しているようです。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2023年11月「線維筋痛症の女性」
「薬剤師の先生ですか?“センイキンツウショウ”に効く漢方薬がありますか?」という電話がありました。最近の傾向ですが、多くの方が、医師の診断名を単刀直入にあげ、「私の様な方がいますか?」「(漢方薬で)治りますか?」と畳み掛けてきます。難病レベルで、西洋医学ではなかなか良い結果が得られず、漢方薬だったらと淡い希望を持っての苦痛の訴えです。近年の西洋医学は科学技術が進み、より細かな診断名が付いています。病態にもよりますが、先生によって、診断名が違うこともよくあります。漢方薬は二千年以上前に確立された医学で、西洋医学のようにミクロな見方でなく、マクロで総合的に病状の情報を集め、「症候群」のような捉え方をします。上記の方も症状の他に生活習慣、住まいの環境、仕事内容、家族構成や痛みや冷えの程度、精神症状がおかしくなった経過を理解できる範囲でお尋ねしました。六十代で御主人のフォーローをする仕事、子供なし、いろいろ人の世話に追われ、気丈に頑張っているが、年齢的な疲れも何となく見えてきました。「漢方薬の方が体調を良くします。体も脳も体力をつけることです。一回ご来店ください、雰囲気だけでもわかればもっと良い処方が見つかりますョ」とお答えし、後日予約をしてご来店の運びとなりました。世の中頑張りすぎている人が多いようです。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2024年5月「人生五訓」
京都嵯峨小倉山二尊院の“あせるな おこるな いばるな くさるな おこたるな”は日常の反省として身にしみる身近な戒めの言葉です。落ち着かない、許せない、身の程知らず、知恵不足、なまけもの、などの似通った単語も浮かびます。いずれも心の状態をうまく言い表しています。漢方でも、心、心理状態を探りながら処方を考えることがよくあります。世間によくあるのは、家族、親と子、嫁と姑、財産問題、上司と部下、同級生同士、恋愛のもつれ、など身の上相談になりそうな背景から、「気」のトラブルが起こったり、「血」の病気を引き起こしたり、「水」による体調不良が起こったりします。漢方では、身体のバランスの崩れや偏りを考えます。一日は24時間でみな平等な時間です。そして、太陽の照る日中と月の出る夜は、季節によるずれはありますが、ほぼ半分づつです。偏ってもまた戻るのです。どちらか一方だけでは続かなくなっています。「気の病(やまい)」と書いて「病気」と言っています。そう、気の安定が大事です。人には思考、感情があるので気は微妙に変化し複雑ですが、気の安定は病の予防や治療に必要です。「心」の「安定」そして「安心」「健康」です。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2024年6月「人生五訓 あせるな」 京都嵯峨小倉山二尊院
初めに「あせるな」。身にしみる一言です。あせった自分の体験。緊張してよけいな一言を喋ってしまって気まずくなりました。あせった!あの時警察に止められたのは、あせってスピードをつい出した結果でした。罰金が痛かった!大失敗!あせって対応がおろそかになり、信用を失いました。はずかしい!良くある事ですが、後になって後悔するものです。心の準備が足りなかったり、能力以上の行動を起こしたり、時間に追われたり、足が地についていない状態ですね。わかっちゃいるけど・・・。起った事実は変えられません。行動や考えに変化をもたらした相手や事象は神様かもしれません。そう!反省を促してくれていますから。漢方で心を落ち着かせる生薬としては「柴胡」「黄連」「竜骨」「牡蠣」「牛黄」「人参」などが入った処方を選びます。自律神経、特に交感神経の緊張を緩めたり副交感神経を高めたりバランスをとる目的があります。「過ぎたるは及ばざるがごとし」身の丈に合った行動が病気を軽くするこつかもしれません。腹式呼吸も良いでしょう。最近は「失敗は成功の元」と慰める肝っ玉の大きい人も見かけますが・・・。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2024年10月「人生五訓 おこるな」 京都嵯峨小倉山二尊院
漢方では「怒ると血が濁る」といわれます。「息も紫色」になると言います。いかにも「気の病」の一つでしょう。「怒りはと肝を破る(肝臓を悪くする)」とも表現されます。経験上、一回ブチ切れると底まで吐き散らかさないとなかなか怒りは収まらず、必ず後悔の念にさいなまれます。漢方薬でイライラや癇癪、眠れない時良く効く「抑肝散」あるいは「抑肝散加陳皮半夏」という処方があります。子供がキーキー言う、あるいはチック(言葉でうまく表現できないため小さな動作を繰り返し訴えてバランスを取る。無意識に目のシパシパまばたきを繰り返したり、口の周りをペロペロなめるなど)に用います。校長先生上がりで肝臓の相談があり、「柴胡加竜骨牡蠣湯」を長く服用して頂きました。うっ血してどす黒かった顔色が少しずつ明るくなり、肝臓値も合わせるように良くなっていきました。「深呼吸をしましょう!」とアドバイスする先生もいらっしゃいます。「貧乏ゆすり」も緊張を緩める動作のひとつと言われます。日頃の運動の習慣も大事です。アルコールは飲み過ぎないように。爆発しないように常にガス抜きをすることです。桜島も小さな噴火は大事で、これがないと大噴火となります。癇癪持ちは損をする。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2025年2月「人生五訓 おこたるな」 京都嵯峨小倉山二尊院
高校時代の話です。数学の先生が担任で「日々題」という数学の宿題がありました。毎日一題一枚持ち帰り、解答、翌朝提出。朝の授業前朝礼の様に正解を発表する、という地獄のような毎日でした。睡眠時間を削っても夜の勉強時間の配分がうまくいかず、手つかずのまま友達の解答を丸写しして提出したこともありました。皆真面目に取り組んでいましたが、今でも思い出すほど苦痛の種でした。遠い遠い昔の話ですが、出来ないなりにはよくやったと思います。英語の副担任にいつも口癖で「継続は力なり!」と、発破をかけられていました。ここまで無理をしなくとも、日常生活の中で、毎日のルーテイーンとして繰り返すことにより自然に身に着くことはたくさんあります。「好きこそものの上手なれ」とも言われますが、そうでなくても、続けることで身に着くことはよくあるのです。体力もそうです。若い時はあまり意識しませんが、歳と共に体力の衰えを感じる頃から、やれ健康食品だのスポーツジムだの意識し出します。「運動してますか?」よくお尋ねしています。「体質改善」という言葉は今はあまり使われていませんが、漢方薬も継続が大事です。“体質を良くする漢方薬”は受け入れやすいと思います。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
「人参」
“ニンジン ”と聞くと、まず、オレンジ色で馬が好物の野菜、セリ科のニンジンを思い浮かべる方が多いかもしれません。一方、ウコギ科の「朝鮮人参」を思い浮かべた方は健康への知識が深い方かもしれません。今回は後者の「人参」の話です。名称がまぎらわしいのですが、朝鮮人参の他に「高麗人参」、「薬用人参」、「オタネニンジンン」など、使用の歴史に沿って色々の名前がついています。国内では初代徳川家康、八代将軍吉宗などが人参の普及に関係しています。人参は栽培年数により一年根から六年根を目安としますが、五~六年根以上が高級品質とされています。一~三年根は中枢の働きを抑えるディオール系成分が多く、五~六年根ではトリオール系という元気をつけたり長生きに役立つ成分が多くなっています。一~三年が子供の人参、五~六年が大人の人参というイメージでしょうか。生薬の種類として、とれたての生の人参を「水参(すいじん)」、水参をそのまま乾燥したものを「白参(はくじん)」、水参を蒸して飴色状になったものを「紅参(こうじん)」と呼んでいます。紅参は白参に含まれる「マロン酸ギンセノサイド」という血圧を上げやすい成分が蒸して除かれており、血圧を気にされる方は紅参をオススメします。「偽人参(ぎにんじん)」もたまに見かけます。キキョウ、トウキ、ヒュウガトウキなどは根がかなり似た形態をしています。それぞれは目的の薬効がありますが、違う植物ですので鑑別が必要です。ここで「人参の七つの効きめ」をご紹介します。補気救(ほききゅう)脱(だつ)、益(えっ)血(けつ)復脈(ふくみゃく)、養(よう)心(じん)安神(あんしん)、生津止渇(せいしんしかつ)、補肺定喘(ほはいていぜん)、健脾止瀉(けんぴししゃ)、托毒合(たくどくがっ)瘡(そう)、以上。何となく意味が解ると思います。漢方では人参単品を用いた「独参(どくじん)湯(とう)」という処方もありますが、通常は数種を混合した処方で使用されています。代表的な漢方薬としては人参(にんじん)湯(とう)、小柴(しょうさい)胡(こ)湯(とう)、補中(ほちゅう)益(えっ)気(き)湯(とう)など、血行を良くしながら滋養強壮、体力強化を目的に使用されています。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎