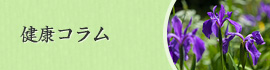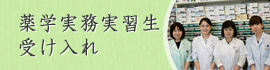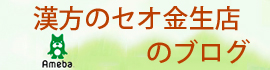皮膚
2023年3月「首下胸上のかゆい男性 」
その日は漢方相談者の対応をしていました。店頭にやせた高齢の男性がスタッフと話をしている姿を見て気になっていました。一旦お帰りになったので、後で内容を尋ねたところ、「ここ一年、首の付け根下から胸上、丁度ランニングシャツの肌が見える部分が痒くて困っている。一番強いステロイド軟膏で痒みが止まるが、次のクラスのステロイド軟膏では効かない。昨晩インスタントラーメンを食べたらひどくなった」という内容でした。再度予約をしてもらい、患部を診たところ、ツキノワグマの胸の白い部分が三日月状に真っ赤になっており、皮膚が薄く、痛々しい(本人は痒くてたまらない)様子でした。汁が出ている様子は見受けられませんでしたが、時間の問題かな~と思いました。皮膚の炎症をとる漢方薬の顆粒、かゆみの原因となる、汗や汚れをとる清拭剤、直接皮膚に塗るセオのローション剤、食事の矯正のために葉緑素の錠剤を差し上げました。一ヶ月後、「先生、半分くらいに痒みが取れました」とご報告。診ると、赤みが大分引いていました。
「今回は煎じ薬の漢方薬に切り替え、しっかり治しましょう」と希望を持ちながらの相談でした。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2023年9月「多汗症の男性」
今年は異常な暑さが続いています。全国的に最高気温更新のニュースが報道される中、昼にお電話がありました。昔から「多汗症」で、異常な“大汗”をかくとのことでした。現在、外での作業が主で急に暑くなり汗が噴き出てくる、熱中症対策で水分はしっかり飲むよう気を付けているとのことでした。個人差はありますが、暑い時に汗をかくことは大事です。体温調節や代謝や血行を良くしたり、皮膚表面の老廃物を排泄する役目があります。過去の相談を思い出しました。上半身の汗を止めるため、脇にある自律神経の神経節を切る施術をされた若い女性、術後汗をかかなくなったまでは良かったのですが、カサカサ肌になってしまい、逆に汗をかく漢方薬をとのことでした。これも悩ましい相談でした。さて、今回は「黄耆(おうぎ)」という生薬を使った漢方薬を選びました。黄耆はマメ科の植物で、元気をつけたり、汗の異常を正したりする生薬です。飲んでいる“水分の明細”を確認したところ、“炭酸入り”で“冷たい”ものをよくとっているようでした。暑いのですが、できるだけ常温で胃腸を冷やさないようにお願いしました。胃が冷えると「肌肉(きにく)」下に水が溜まり、暑い中では一気に汗が噴き出すからです。おまけで“夏場の涼める食品”の話もしてあります。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
2023年12月「背中が痒い80代女性 」
皮膚病の相談で問合せが入り、後日相談日を連絡予定していました。翌月曜日の朝「今から来たい」と連絡がありあわてて対応しました。患部を見せてもらうと、左肩肩甲骨にそって掻いた跡が赤く腫れており、一部は周りにブツブツがみられました。「いつからかゆいのですか?」「ここ数年。きのうは特に痒くなって掻いてしまった」いろいろ問診が続きます。医師の食べ物のアレルゲンの検査結果では何もひっかかっておらず、わからないとのこと。医療用の漢方薬も合わなかった。「昨日は何を食べましたか?」一つ一つねちねちと質問します。すると、「明太子」がやっと出てきました。「先生の検査ではこれはありませんもんねぇ」となぐさめ、ピリ辛で刺激物、卵が原料加工品のため反応しやすかった事を説明しました。他にも原因になりやすい食品をたくさん好んで食べており、「治るのにはかなり時間がかかる」ことをお伝えしました。年齢の割には若くはつらつとされており、患部以外の皮膚はシミもなく綺麗な皮膚をしておられました。熱を持ちやすい場所の為、気温の高い時は痒みがひどくなることが予想されます。頑張りましょう!
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
「人参」
“ニンジン ”と聞くと、まず、オレンジ色で馬が好物の野菜、セリ科のニンジンを思い浮かべる方が多いかもしれません。一方、ウコギ科の「朝鮮人参」を思い浮かべた方は健康への知識が深い方かもしれません。今回は後者の「人参」の話です。名称がまぎらわしいのですが、朝鮮人参の他に「高麗人参」、「薬用人参」、「オタネニンジンン」など、使用の歴史に沿って色々の名前がついています。国内では初代徳川家康、八代将軍吉宗などが人参の普及に関係しています。人参は栽培年数により一年根から六年根を目安としますが、五~六年根以上が高級品質とされています。一~三年根は中枢の働きを抑えるディオール系成分が多く、五~六年根ではトリオール系という元気をつけたり長生きに役立つ成分が多くなっています。一~三年が子供の人参、五~六年が大人の人参というイメージでしょうか。生薬の種類として、とれたての生の人参を「水参(すいじん)」、水参をそのまま乾燥したものを「白参(はくじん)」、水参を蒸して飴色状になったものを「紅参(こうじん)」と呼んでいます。紅参は白参に含まれる「マロン酸ギンセノサイド」という血圧を上げやすい成分が蒸して除かれており、血圧を気にされる方は紅参をオススメします。「偽人参(ぎにんじん)」もたまに見かけます。キキョウ、トウキ、ヒュウガトウキなどは根がかなり似た形態をしています。それぞれは目的の薬効がありますが、違う植物ですので鑑別が必要です。ここで「人参の七つの効きめ」をご紹介します。補気救(ほききゅう)脱(だつ)、益(えっ)血(けつ)復脈(ふくみゃく)、養(よう)心(じん)安神(あんしん)、生津止渇(せいしんしかつ)、補肺定喘(ほはいていぜん)、健脾止瀉(けんぴししゃ)、托毒合(たくどくがっ)瘡(そう)、以上。何となく意味が解ると思います。漢方では人参単品を用いた「独参(どくじん)湯(とう)」という処方もありますが、通常は数種を混合した処方で使用されています。代表的な漢方薬としては人参(にんじん)湯(とう)、小柴(しょうさい)胡(こ)湯(とう)、補中(ほちゅう)益(えっ)気(き)湯(とう)など、血行を良くしながら滋養強壮、体力強化を目的に使用されています。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎