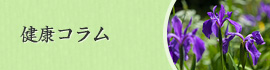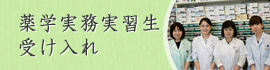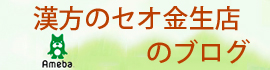消化器
2025年1月「人生五訓 くさるな」 京都嵯峨小倉山二尊院
毎日一生懸命真面目にしていても、失敗したりタイミングにより咎められることがあります。落ち着いた真摯な反省は必要でしょう。諦めずに先に生かす気持ちが自分を育ててくれます。どうしても過去を気にすることがありますが、事実は変えることはできません。「あの時こうしていたら・・・」ということはよく経験することです。「過去は変わりませんが未来を変えることは可能ですよ!」と相談のお客様を励まします。多くの「成功者」は、たくさんの失敗を恐れずにあるいは乗り越えて、目標を失わず前進した結果、大きなものを掴んでいるようです。くさることもあることでしょう。でも次のステップに気持ちを早く切り替えることも大事なことです。気を上向きにする漢方薬は・・・?補中益気湯、半夏厚朴湯、柴胡加竜骨牡蠣湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、加味逍遥散、加味帰脾湯、タイプタイプによりいろいろの処方があります。最近冷たい物を口にしている方がよく目につきます。舌を見ると、冷えて白っぽく血の色がいかにも薄い感じです。これでは食物からの栄養(気)を消化吸収するのに力不足で、消化不良、まさに“くさる”のです。胃の元気は健康に直結します。胃を助ける漢方薬も大事ですね。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
「2025年 薬草の集いinサマー 」
7月末、土用の中日、炎天下の暑い暑い日曜日、溝辺空港山奥の「薬草の森」へ、イベントの係で参加しました。夏休みの為、小学生を中心に多くの家族連れでにぎわいました。午前中は理科の先生を先導に植物採集、薬剤師による薬草教室、薬草を使った草木染、午後より、植物採集の先生方による植物の名付と標本作成指導、薬剤師の薬草園案内、草木染、新企画で紙すき体験(外部委託)、がそれぞれの担当で手分けして開催されました。私は中央駅からバス希望の方の案内で往復同乗しました。行きの到着までの約1時間、薬草の森の歴史や身近な薬草の話をしました。夏はウリ科の野菜類が体には良いです。ニガウリ(ゴーヤ)、キュウリ、トウガン、スイカ、ヘチマ、少しするとカボチャ。暑い季節に涼めてくれます。オクラなど添えるとネバネバが体に効きそうですね。人工的な冷蔵物などで胃が冷えると急に汗が止まりますが、汗で体温を下げられなくなり熱が皮膚下で体の中にこもるのです。益々暑く感じ、冷たい物が欲しくなり、胃腸が冷えすぎてしまいます。そう、夏バテが早く来ます。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎
「人参」
“ニンジン ”と聞くと、まず、オレンジ色で馬が好物の野菜、セリ科のニンジンを思い浮かべる方が多いかもしれません。一方、ウコギ科の「朝鮮人参」を思い浮かべた方は健康への知識が深い方かもしれません。今回は後者の「人参」の話です。名称がまぎらわしいのですが、朝鮮人参の他に「高麗人参」、「薬用人参」、「オタネニンジンン」など、使用の歴史に沿って色々の名前がついています。国内では初代徳川家康、八代将軍吉宗などが人参の普及に関係しています。人参は栽培年数により一年根から六年根を目安としますが、五~六年根以上が高級品質とされています。一~三年根は中枢の働きを抑えるディオール系成分が多く、五~六年根ではトリオール系という元気をつけたり長生きに役立つ成分が多くなっています。一~三年が子供の人参、五~六年が大人の人参というイメージでしょうか。生薬の種類として、とれたての生の人参を「水参(すいじん)」、水参をそのまま乾燥したものを「白参(はくじん)」、水参を蒸して飴色状になったものを「紅参(こうじん)」と呼んでいます。紅参は白参に含まれる「マロン酸ギンセノサイド」という血圧を上げやすい成分が蒸して除かれており、血圧を気にされる方は紅参をオススメします。「偽人参(ぎにんじん)」もたまに見かけます。キキョウ、トウキ、ヒュウガトウキなどは根がかなり似た形態をしています。それぞれは目的の薬効がありますが、違う植物ですので鑑別が必要です。ここで「人参の七つの効きめ」をご紹介します。補気救(ほききゅう)脱(だつ)、益(えっ)血(けつ)復脈(ふくみゃく)、養(よう)心(じん)安神(あんしん)、生津止渇(せいしんしかつ)、補肺定喘(ほはいていぜん)、健脾止瀉(けんぴししゃ)、托毒合(たくどくがっ)瘡(そう)、以上。何となく意味が解ると思います。漢方では人参単品を用いた「独参(どくじん)湯(とう)」という処方もありますが、通常は数種を混合した処方で使用されています。代表的な漢方薬としては人参(にんじん)湯(とう)、小柴(しょうさい)胡(こ)湯(とう)、補中(ほちゅう)益(えっ)気(き)湯(とう)など、血行を良くしながら滋養強壮、体力強化を目的に使用されています。
セオ薬局代表取締役 漢方薬・生薬認定薬剤師 瀬尾昭一郎